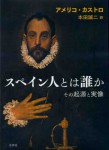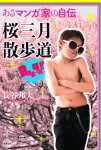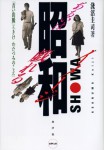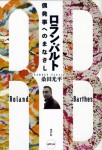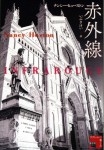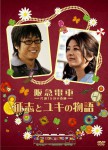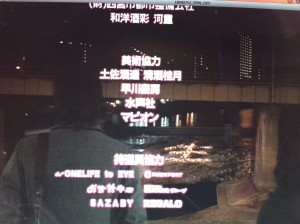書評:ネグリ思想の精髄
2012年 2月 3日
 昨年11月に刊行されて以来、根強く読者を獲得しているのが、
昨年11月に刊行されて以来、根強く読者を獲得しているのが、
イタリアの思想家、アントニオ・ネグリの
「スピノザとわたしたち』(信友建志訳)。
1月29日付の朝日新聞読書面(ニュースの本棚)では
「スピノザが来た」と題されたコラムで
紹介されたこともあって(*)、
お問い合わせの電話を多数いただいております。
本書はいっけん難解なスピノザ×ネグリの対決でありながら、
「ネグリによる現代スピノザ入門」として読むことも可能なのですが、
年末の『 図書新聞』紙に掲載された杉村昌昭さん(龍谷大学名誉教授)の
書評が、本書のきわめて明晰な解説にもなっているので、
杉村さん、および図書新聞さんの許可をいただいたうえで、
ここに再掲させていただきます。
ぜひ、本書をひもとくさいの参考にしてください!
—–
ネグリ思想の精髄——スピノザをポスト近代の思想家として定位する
杉村昌昭
チュニジアに始まったアラブ革命はまたたくまにアラブ世界全域に広がり、少し遅れてギリシャの債務危機をきっかけにスペインから始まった “怒れる者たち” の反世界金融権力の運動は大西洋をわたってウォール・ストリートの占拠活動にまでいたった。しかし、十年以上前に『帝国』で世界デビューしたアントニオ・ネグリの思想は、こうした現状を一種予言的に示唆したものであるにもかかわらず、このかん衰退して久しい感がある。奇妙なもので、歴史に先がけて提示した世界の見取り図が現実にその軌跡を描き始めると忘れられていくのである。そのネグリは3年前(2008年)にG8サミットが北海道で開催された年、当時企画されていた日本における反サミットの運動とは無関係であったにもかかわらず日本入国を拒否された。しかしネグリを改めて招請する企画が昨年(2010年)から始まっていて、シンポジウムの日程などもほぼ本決まりになった時点で、3月11日の東日本大震災が起きてオジャンになったという(これはもともと東京アカデミズムの動向に疎遠な私が人伝に聞いた話で、どこのどなたがこれを企画したのか、詳しいことは寡聞にして知らない)。ネグリはよほど日本と縁のない人物なのかもしれない。
それに反してスピノザはいまも『エチカ』がよく読まれ、専門的な研究雑誌が刊行され続けてもいるのだから、マルクスとまではいかなくても、もっと日本と親和性があるのかもしれない。その日本に縁のないネグリが縁のあるスピノザについて著したのが本書である。
ともあれ、ネグリが本書で試みているのはスピノザをポスト近代の思想家として定位することである。もともとネグリは獄中で書いた『野生のアノマリー——スピノザにおける力能と権力』以来、ことあるごとにスピノザを “今日化” し “現働化” することに意を注いできた。そのエッセンスが本書『スピノザとわたしたち』であると言っていいだろう。
では、スピノザはなにゆえポスト近代の思想家であるとネグリは言うのだろう。それは主にスピノザのコナトゥス(自存力)という概念の解釈にかかわる。コナトゥスとは、スピノザによると「あらゆるものはその存在のなかに居続けようと努力する」という「もの」の傾向性の謂だが、この「もの」とは、宇宙の万物であり、拡大解釈すれば、自然界という存在から人間がつくりだしたすべてのもの、集団、企業、国家などあらゆる社会的制度や組織、あるいは思想的産物や芸術作品など抽象的なものまでも含む広大な射程を持ったものとして理解することができる。
しかし、こうした「もの」を人間の社会的創造物に限定して政治思想的観点からその生成変化の相でとらえると、それは保守的にも革新的にも解釈可能である。たとえば3月11日の大震災と原発事故以降、日本政府、経済産業省、東京電力といった組織体はこれまでどおりの「存在のなかに居続けようと」必死になって努力している。これもコナトゥスのなせるわざであろう。一方、日本国民はこうした行政権力や経済権力の動きに異を唱えながらも、どうしようもなく「自らの存在のなかに居続ける」道を選んでいるように見える。いつになったら、「自らの存在」を内側から壊して変身することになるのか、予測がむつかしい。しかし他方で、少なくとも「自らの存在のなかに居続ける」ためにも、自らが変化するしかないという刷新の気分も醸成されてきている。そのような情動が大きなうねりとなったとき初めて、コナトゥスがその革新的力を発揮することになるのかもしれない。
とはいえ、現状は “あれかこれか”(たとえば原発維持か原発廃絶か)という二項対立的な選択を迫られているように見えながら、実は “あれもよしこれもよし”( “脱原発” という表現にしても、原発をやめようと言いながら続けていくという一種自己矛盾的な二重肯定の吐露ではないか)が社会空間に瀰漫している。これはコナトゥスが日本的に機能している状態と言わねばなるまい。言い換えるなら保守的コナトゥスの支配する日本的なポスト近代の断面であり、こういう回路で日本社会はスピノザ哲学と親和性があるのだ。しかしネグリがスピノザのコナトゥスを援用しながら切り開こうとするポスト近代の風景は当然のごとくこれとは異なる。そこに底流するのはコナトゥスの革新的解釈である(これについてはあとで述べよう)。
いずれにしろ、コナトゥスとは状況によって保守的にも革新的にも作動する両義性を持った力であると考えることができるだろう。こうした一種特異な普遍性を帯びるべく錬成された概念は、必然的に相対立することもある複数的解釈が可能な領域を切り開く。たとえばドゥルーズ/ガタリの “リゾーム” という概念がそうだ。フロイトの無意識をポジティブに言い換えたこの概念は、社会変動あるいは組織編成の場面に適用すると、深い変革をもたらす革命的概念にもなりうる一方、軍隊や企業が旧来のピラミッド型の組織構造からより効果的な横断的編成構造(軍事で言うなら“ゲリラ戦術”)に転換するときの功利的なキー概念にもなりうる(実際 “リゾーム” をビジネス活動の組織編成に応用した論文もある)。
ネグリはコナトゥスを革命的進路の模索に適用し、すみずみまで内部化された世界(諸個人に内在する多様な分子的要素は社会、国家を超えて、世界全体にまで連鎖している)における革命主体としてマルチチュードという概念をひねりだす。世界を内側から破壊して革命的再創造を可能にするのは、この内部世界における多数者としてのマルチチュードの情動に依拠した力能しかないというわけだ。これは代表制民主主義を底支えする近代の二項対立図式(たとえばブルジョア資本権力対プロレタリ革命勢力といった)からの脱却であり、したがって賞味期限のきれた代表制民主主義を乗り越えるポスト近代民主主義の素描にほかならない。
本書は、内在性、民主制、力能、情動というスピノザから抽出した四つのキー概念を駆使して近代の政治思想に対する先進的な批判を展開しながら、《共同性》という古くて新しい概念を独自に刷新して《共》(コモン)という概念を創出し、ポスト近代の政治的地平を展望しようとするネグリ思想の精髄と言えるだろう。このネグリの思想的展望をどう解釈するかはわれわれに課された課題だが、訳者の信友建志が力のこもった「解説」のなかで、そのすぐれた実践例を提示している。(龍谷大学名誉教授・現代思想)
*『図書新聞』2011年12月24日号
*なお、杉村さんによる最新の翻訳でジャン=クレ・マルタンによる
『フェルメールとスピノザ——〈永遠〉の公式』も、
以文社さんから好評発売中です。あわせてご覧ください!
Courtesy of Mr. Masaaki Sugimura and Toshoshimbun.